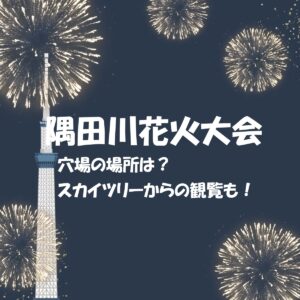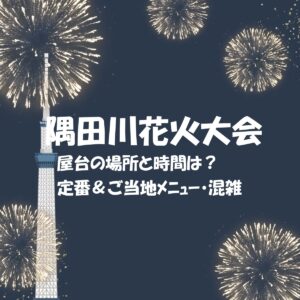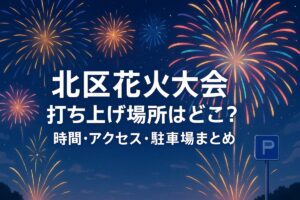日本三大美祭のひとつとして知られる「高山祭(たかやままつり)」。
毎年春と秋に岐阜県高山市で開催されるこのお祭りは、豪華絢爛な屋台(やたい)や、伝統あるからくり人形、幻想的な夜のライトアップなど、見どころ満載のイベントです。
2025年の春の高山祭では、どんなスケジュールで行われるのか?
どこを見れば最大限に楽しめるのか?
そして、そもそも高山祭とはどんな祭りなのか?
この記事では、高山祭2025年春の開催日程や見どころ、歴史、アクセス情報まで、初めて訪れる方にもわかりやすくまとめます!
高山祭とは?日本三大美祭の一つを紹介!
高山祭(たかやままつり)は、岐阜県高山市で開催される伝統的なお祭りで、春の「山王祭(さんのうまつり)」と秋の「八幡祭(はちまんまつり)」の年2回にわたって行われます。
その美しさと歴史的価値の高さから、京都の祇園祭、埼玉の秩父夜祭と並ぶ「日本三大美祭」のひとつとして知られています。
起源は江戸時代までさかのぼります
高山祭の起源は、江戸時代中期(17世紀後半)にさかのぼるとされています。
町人文化が花開いたこの時代、高山の商人たちが競って豪華な屋台(やたい)を作り、それを披露する形で祭りが発展していきました。
もともとは氏神への感謝と五穀豊穣を願う神事でしたが、時代とともに華やかな要素が加わり、現在のような祭りの形になりました。
まるで動く芸術品!豪華な屋台
高山祭を象徴する存在が、精巧な彫刻や漆塗り、金箔などで装飾された「屋台」です。
その豪華さから「動く陽明門」とも称されることも。
春の祭りでは12台前後、秋には11台前後の屋台が登場し、町をゆっくりと練り歩きます。
中には、からくり人形が組み込まれた屋台もあり、祭り期間中には「からくり奉納」と呼ばれるパフォーマンスも行われ、多くの観光客を魅了しています。
ユネスコ無形文化遺産にも登録
2016年には、高山祭の屋台行事が「山・鉾・屋台行事」として、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。
地域に根ざした伝統が、現代まで受け継がれている点が高く評価されています。
 碧
碧高山祭は歴史・芸術・伝統が融合した、日本を代表するお祭りなんです。
春の高山祭2025の開催日程と基本情報
2025年の春も、待ちに待った高山祭の季節がやってきます。
毎年4月14日・15日に行われる春の高山祭は、地元では「山王祭(さんのうまつり)」として親しまれ、日枝神社の例祭として開催されます。
ここでは、2025年春の高山祭の開催日程や会場、アクセス方法など、基本情報をまとめます。
日程と場所
開催日程
開催日:2025年4月14日(月)・15日(火)



日付は毎年固定されており、曜日に関係なく開催されます。
主な会場・神社
開催地:岐阜県高山市中心部(旧市街地一帯)
祭神:日枝神社(ひえじんじゃ)
日枝神社を中心に、高山市の古い町並みを背景にして祭りが繰り広げられます。
春の柔らかな陽射しと、江戸情緒あふれる町並みのコントラストが見どころの一つです。
主なイベントスケジュール(予定)
【4月14日】
宵祭(夜):屋台に提灯が灯され、幻想的な夜の巡行が行われます
屋台曳き揃え(昼):装飾された豪華な屋台が一堂に並び、見応え抜群
からくり奉納(昼):精巧なからくり人形が屋台の上で演舞
【4月15日】
屋台曳き揃え・からくり奉納(再演)
御巡幸(ごじゅんこう):神様を乗せた神輿が町を巡行
※天候などにより一部イベントが中止または変更となる場合があります。
アクセス
- 【電車】JR高山本線「高山駅」から徒歩10~15分
- 【車】名古屋から約2時間半(東海北陸自動車道 経由)
- 【注意】祭り期間中は交通規制があるため、公共交通機関の利用がおすすめです。



高山祭は国内外から多くの観光客が訪れる人気イベントです。特に春は観光シーズンとも重なり、ホテルや交通機関が混み合うことが予想されます。
\10日前から予約可能 !時間内入出庫OK/
見逃せない!高山祭の主な見どころ3選
高山祭といえば、伝統と美が融合した豪華な祭礼。
その中でも「これは絶対に見逃せない!」という注目ポイントを3つ厳選してまとめます。
初めて訪れる方も、リピーターの方も、これを押さえれば高山祭をより深く楽しめますよ。
豪華絢爛な「屋台曳き揃え」
高山祭最大の見どころが、屋台(やたい)と呼ばれる山車が一堂に揃う「曳き揃え(ひきぞろえ)」です。
彫刻や漆塗り、金箔で装飾された屋台は、まさに“動く美術館”。
昼間はその豪華な細部までじっくり鑑賞でき、屋台ごとに個性あるデザインを楽しめます。
特に春の祭りでは、日枝神社に奉納される12台前後の屋台が旧市街に並び、その迫力ある姿は写真映えも抜群です!
からくり人形の奉納演技
屋台の中には、からくり人形が搭載された「からくり屋台」があり、祭り期間中に「からくり奉納」が行われます。
これは、精巧な仕組みで人形が舞を披露するパフォーマンスで、江戸時代の技術の高さに驚かされます。
人形が笛や太鼓に合わせて動く様子は、まるで生きているかのようなリアルさ。
子どもから大人まで、思わず見入ってしまう人気の演目です。
幻想的な「宵祭(よいまつり)」
夜になると、屋台に無数の提灯が灯され、幻想的な雰囲気に包まれるのが「宵祭」。
昼とは一転、闇に浮かび上がる屋台は、まさに非日常の世界を演出してくれます。
提灯のほのかな灯りと、夜の高山の静けさの中で行われる屋台の巡行は、どこか神秘的で幻想的。
写真や動画に残すにも最適な時間帯です。



どの見どころも、高山祭の魅力を体感できる貴重なシーンばかり。限られた時間でまわるなら、これら3つはぜひチェックしておきたいポイントです!
豪華絢爛な屋台行列とからくり奉納の魅力
高山祭の魅力を語るうえで欠かせないのが、「屋台行列」と「からくり奉納」です。
歴史と職人技が詰まったこれらの見せ場は、高山祭が“日本三大美祭”と呼ばれる理由そのもの。
ここでは、それぞれの魅力をじっくりご紹介します。
豪華絢爛!伝統が息づく屋台行列
高山祭のシンボルともいえる「屋台」は、まるで芸術品のような美しさ。
漆や金箔、極彩色の彫刻で飾られた屋台は、江戸時代から受け継がれた職人の技術が詰まった傑作です。
春の高山祭(山王祭)では、12台前後の屋台が町中を練り歩きます。
これを「屋台行列(曳行/ひきまわし)」といい、揃って動くその姿は圧巻。
木の車輪が石畳をきしむ音や、囃子(はやし)の音色が響く中を進む様子は、時代を超えた世界へと誘ってくれます。
また、屋台はそれぞれにテーマやデザインが異なり、「〇〇台」と名前がついているのも注目ポイント。
お気に入りの屋台を見つけてみるのも楽しいですよ。
見逃せない「からくり奉納」
いくつかの屋台には、「からくり人形」が搭載されており、祭り期間中に演技が披露されます。これが「からくり奉納」と呼ばれるもので、特に春の高山祭では人気のイベントのひとつです。
からくり人形は、糸や歯車を巧みに使って動かされる伝統工芸の結晶。
まるで生きているかのように舞い、踊り、道具を扱う姿は、初めて見る人なら誰もが驚きと感動を覚えるはずです。
演技は数分程度の短いものですが、背景には緻密な準備と高い技術が詰まっています。
人形の動きと演奏のタイミングがピタリと合った瞬間は、まさに“匠の芸”を目撃した感覚に。
屋台・からくりをじっくり楽しむコツ
- 屋台は午前中~午後の曳き揃え時が見頃!
- からくり奉納はスケジュールを事前にチェック!
- 混雑が予想されるので、30分以上前の場所取りがおすすめ!



豪華絢爛な屋台と、心を打つからくり奉納は、高山祭の醍醐味そのもの。目で見て、耳で聴いて、心で感じる…五感で味わう日本の伝統を、ぜひ現地で体感してみてくださいね。
夜の幻想!宵祭りとライトアップの楽しみ方
日中のにぎやかさとは一転、夜の高山祭はしっとりとした幻想的な雰囲気に包まれます。
中でも、「宵祭(よいまつり)」は、提灯に灯がともる美しい屋台の巡行が見どころです。
歴史ある町並みとあいまって、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような体験ができます。
宵祭とは?
「宵祭」とは、4月14日の夜に行われる夜間の屋台曳行のこと。
昼間とは違い、屋台に数十個の提灯が飾られ、ほのかな灯りに照らされながら静かに町を巡ります。
提灯のやさしい光が、漆や金箔で彩られた屋台を美しく浮かび上がらせる様子は、まさに「動く灯籠」。
屋台が進むにつれて、笛や太鼓の音が夜の町に響き渡り、観客は静かにその幻想的な光景に見入ります。
幻想的な雰囲気を楽しむコツ
- 早めの場所取りがポイント!
人気のルート沿い(上三之町エリアなど)は特に混雑するため、宵祭が始まる1時間ほど前には現地に着いておくのがおすすめです。 - カメラやスマホは夜景モードに!
宵祭のライトアップは暗めなので、写真を撮る際は夜景モードや三脚を使うときれいに撮れます。 - 夜は冷え込むこともあるので、防寒対策を忘れずに
春とはいえ高山は山間部。
夜は冷えることもあるので、上着やストールを一枚持っていくと安心です。
ライトアップの屋台を背景に記念撮影も◎
屋台が並ぶポイントでは、ライトアップされた屋台を背景に記念撮影する人もたくさんいます。
提灯の光と歴史的建造物が合わさった高山の夜景は、旅の思い出としても最高の一枚になるはずです。



日中の華やかさとはまた違った、静かで幻想的な「宵祭」。ぜひ夜まで滞在して、この特別な時間を楽しみましょう。
高山祭の歴史と由来とは?伝統のルーツを解説
日本三大美祭に数えられる高山祭。
その華やかさや精巧な屋台に目を奪われがちですが、実はこのお祭りには数百年の歴史と深い由来があります。
ここでは、高山祭がどのように生まれ、受け継がれてきたのかをわかりやすくまとめます。
起源は江戸時代中期
高山祭の起源は、17世紀後半の江戸時代中期にさかのぼります。
当時の高山は、幕府の直轄領(天領)として、商業や工芸が発展した城下町でした。
その繁栄の中で、町人たちが自らの力と誇りを表す手段として、豪華な屋台を作り始めたのが祭りの始まりだとされています。
春の「山王祭」は、日枝神社(ひえじんじゃ)の例祭として行われ、五穀豊穣や町の安全を祈願する神事が由来となっています。
町人文化と職人技の結晶
高山祭の特徴である美しい屋台は、まさに町人文化の象徴。
木工・彫刻・漆芸・金工などの匠の技が集結し、それぞれの屋台は数年がかりで作られました。
屋台には「〇〇台」と名前があり、各町が競い合うようにその豪華さを追求していったと言われています。
また、祭りの運営は現在でも「屋台組」と呼ばれる町内ごとの保存会によって支えられており、地域一体となって伝統を守り続けているのも高山祭の魅力です。
秋の高山祭との違いは?
高山祭は春と秋の2回行われますが、それぞれ祭神が異なります。
- 春(4月14・15日):山王祭(日枝神社)
- 秋(10月9・10日):八幡祭(櫻山八幡宮)
どちらも屋台が曳かれ、からくり奉納が行われますが、屋台の種類や装飾、演目に微妙な違いがあるため、春・秋それぞれ訪れて楽しむ人も多いです。



この歴史を知ることで、祭りをより深く、感動的に楽しめると思います。
アクセス・混雑回避・服装のポイント
高山祭を思いきり楽しむためには、事前の準備がとても大切です。
ここでは、アクセス方法や混雑を避けるコツ、そして春の高山に合った服装のポイントをまとめます。
快適に、そしてスムーズに祭りを満喫するために、参考にしてくだされば幸いです!
アクセス方法
【電車で行く場合】
- JR高山本線「高山駅」から徒歩約10~15分
⇒ 高山駅を出てすぐ、祭りムードに包まれた町並みが広がっています。
【車で行く場合】
- 名古屋方面から:東海北陸自動車道・中部縦貫道経由で約2時間半
- 長野方面から:長野道~安房峠道路経由で約2時間
※ただし、祭り期間中は市街地に交通規制がかかるため、車の乗り入れは困難になることがあります。
市内の臨時駐車場を利用し、シャトルバスや徒歩で移動するスタイルがおすすめです。
\事前予約で安心・スムーズ/
2週間前~利用直前まで、スマホ・PCで簡単予約!
混雑回避のコツ
高山祭は国内外から多くの観光客が訪れるため、駅や観覧エリアはかなりの混雑が予想されます。
少しでも快適に動けるように、以下のポイントを押さえておきましょう!
- 早朝の移動がベスト!
屋台曳き揃えやからくり奉納が始まる前に、現地に到着しておくと比較的空いています。 - 昼と夜の間の時間帯は比較的空いている
午後3時~5時頃は観覧の谷間になりやすく、休憩や買い物におすすめ。 - 平日の開催年は狙い目!
2025年の春の高山祭は月曜・火曜に開催されるため、週末よりはやや混雑が緩和される可能性があります。
春の高山におすすめの服装
高山は標高が高く、4月中旬でも朝晩は冷え込むことがあります。
日中はポカポカ陽気でも、夜の宵祭や早朝の移動時には思った以上に寒さを感じるかもしれません。
- 日中:長袖シャツ+薄手の上着(パーカーやカーディガン)
- 朝晩・夜の宵祭:軽めのダウンジャケットやウィンドブレーカーが安心
- 靴:石畳や坂道も多いため、歩きやすいスニーカーやフラットシューズがベスト
また、突然の雨や強風に備えて、折りたたみ傘やカッパ、風よけのストールがあると重宝しますよ。
おすすめの持ち物
- モバイルバッテリー(写真や動画撮影で電池が減りやすい!)
- レジャーシート(場所取りや休憩用に)
- 小銭・現金(露店や地元のお店での支払いに便利)
- 飲み物(特に日中の屋台観覧時に)



しっかり準備しておけば、高山祭はもっと快適に、もっと楽しく過ごせます!
\大容量だから安心!小型軽量です/
地元グルメも満喫!祭りと一緒に楽しみたい名物料理
高山祭を楽しむなら、地元の美味しいグルメもぜひ味わってほしいポイントのひとつ。
古い町並みに並ぶ食べ歩きグルメや、飛騨地方ならではの郷土料理は、旅の思い出をより深いものにしてくれます。
ここでは、高山で絶対に食べたい名物料理をご紹介します!
飛騨牛グルメ(握り寿司・串焼き・ステーキ)
高山といえば、やっぱり飛騨牛!
柔らかく甘みのある上質な肉質で、地元民にも観光客にも大人気です。
- 飛騨牛にぎり寿司:とろけるような生の飛騨牛を酢飯とともに。
お店によってはバーナーで炙って提供してくれるところも! - 飛騨牛串焼き:祭りの屋台や商店街の露店で手軽に味わえる絶品グルメ。
おやつにもぴったり。 - 飛騨牛ステーキやすき焼き:ちょっと贅沢したいときにおすすめの逸品。
夜の食事にも◎。
みたらし団子(高山風)
高山のみたらし団子は、甘くない醤油味が特徴!
香ばしく焼かれた団子に、たまり醤油を塗って仕上げるシンプルな味わいは、素朴ながらもクセになる美味しさ。
一本100円〜と手軽で、食べ歩きにもぴったりです。
高山ラーメン(飛騨中華そば)
地元民にも愛されるB級グルメが「高山ラーメン」。
あっさりとした醤油ベースのスープに、細めのちぢれ麺が特徴で、どこか懐かしさを感じる味。
観光の合間に立ち寄れるラーメン店も多数あり、寒い日には体もぽかぽかになります。
五平餅(ごへいもち)
岐阜や長野など中部地方の郷土食、五平餅も外せません。
ご飯をつぶして串にさし、味噌だれやクルミだれを塗って香ばしく焼き上げた逸品。
もちもち食感と甘じょっぱい味わいで、おやつにも軽食にもぴったり。
高山名物
— ぺんぺん (@STYXHELIX_) September 22, 2024
五平餅 pic.twitter.com/t0C6If2QYn
地酒・飛騨の地ビール
祭りのあとや夜のひとときには、地酒やクラフトビールを味わうのもおすすめです。
- 飛騨の地酒:高山には歴史ある酒蔵が点在し、見学や試飲ができる場所も多いです。
お土産にも◎。 - 飛騨高山麦酒などのクラフトビール:地元の水と素材を活かした、個性豊かな味わいが魅力。



美しい祭りと一緒に、飛騨ならではの味わいを心ゆくまで堪能してみてはいかがでしょうか。
まとめ
高山祭は、歴史ある伝統行事と職人の技、そして地域の誇りが詰まった日本屈指の祭りです。
2025年の春も、4月14日・15日の2日間にわたって、豪華な屋台やからくり奉納、幻想的な宵祭など、見どころ満載で開催されます。
また、祭りと一緒に楽しみたい飛騨牛や高山ラーメンなどの地元グルメも、高山旅行の大きな魅力のひとつ。
アクセスや混雑回避のコツ、服装のポイントなども事前にチェックしておけば、当日も安心して楽しめます。
2025年の春は、ぜひ高山を訪れて、目で見て、耳で聞いて、舌で味わいながら、五感で感じる「本物の日本の祭り」を体験してみてはいかがでしょうか。
忘れられない思い出になること間違いなしですよ!
最後まで読んでくださりありがとうございました。
\比較的予約が取りやすい穴場の宿です/